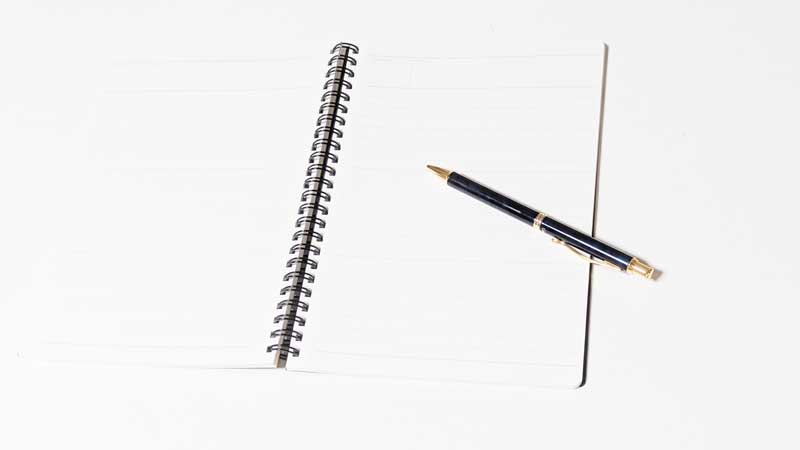大地の成り立ちと変化
火山活動
Q. 地下にあるマグマが地表に噴出してできた山を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は地球内部で岩石がとけて液体状となった高温の物質である。
Q. 一般的にマグマのねばりけが高いほど、火山の傾斜は【 ? 】なる。
Q. マグマのねばりけはマグマに含まれる【 ? 】の割合によって決まる。
A. 二酸化ケイ素 (SiO2)
Q. マグマや火山灰などが地表に噴出する現象を【 ? 】という。
Q. 火山の噴火によって噴出したものを【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は火山砕屑物の1つで、直径2mm以下の粒をいう。
Q. マグマが地表に流れ出したものや、それが冷えて固まったものを【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は、溶岩が冷えて固まるときに、火山ガスが噴き出して小さな穴がたくさんあいた岩石である。
火成岩
Q. マグマが冷えて固まってできた岩石を【 ? 】という。
Q. マグマが地表または地表近くで急激に冷えて固まってできた火成岩を【 ? 】という。
Q. マグマが地下の深いところでゆっくりと冷えて固まってできた火成岩を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は火山岩に特有の組織で、石基(細かい粒)の中に斑晶(鉱物の大きな結晶)が散らばっている。
Q. 【 ? 】は斑状組織にみられる組織の一部で、細かい鉱物の結晶やガラス質でできている。
Q. 【 ? 】は斑状組織にみられる組織の一部で、石基と比べて鉱物の結晶が大きいものをいう。
Q. 【 ? 】は深成岩に特有の組織で、すべての鉱物の結晶が大きく成長している。
Q. 【 ? 】は無色または白色の鉱物で、不規則な形をしている。六角柱状で透明な結晶は水晶という。
Q. 【 ? 】はほぼ白色またはうすい桃色をしている鉱物で、柱状または短冊状の形をしている。ほとんどの火成岩に含まれている。
Q. 【 ? 】は緑黒色をしている鉱物で、長い柱状や針状をしている。
Q. 【 ? 】は暗緑色または暗褐色をしている鉱物で、短い柱状をしている。
Q. 無色または白色をしている鉱物を【 ? 】という。
Q. 黒っぽい暗い感じの色をした鉱物を【 ? 】という。
地震
Q. 地球内部の変動によって大地がゆれ動く現象を【 ? 】という。
Q. 地震が発生した地球内部の場所を【 ? 】という。
Q. 震源の真上にある地表の地点を【 ? 】という。
Q. 地震のはじめの小さなゆれを【 ? 】という。
Q. 初期微動のあとに続いて来る大きなゆれを【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は初期微動を引き起こす地震波である。
Q. 【 ? 】は主要動を引き起こす地震波である。
Q. P波が到着してからS波が到着するまでの、初期微動が続く時間を【 ? 】という。
A. 初期微動継続時間 (P-S時間)
Q. 【 ? 】は地震のゆれを記録する装置である。
Q. 地震を観測した地点でのゆれの程度は【 ? 】で表される。
Q. 地震によって海底で隆起・沈降が起こると、【 ? 】が発生することがある。
地球内部の動き
Q. 地球の表面をおおっている、厚さ100km程の岩盤を【 ? 】という。
Q. プレートのうち、上が大陸であるものを【 ? 】という。
Q. プレートのうち、上が海の底であるものを【 ? 】という。
Q. 地層にできた割れ目の面に沿って、両側に生じているくいちがいを【 ? 】という。
Q. 海底で細長く深いみぞになっている場所のことを【 ? 】という。
地層の重なりと過去の様子
Q. 土砂・火山灰などが層状に堆積したものを【 ? 】という。
Q. 水・風などにより岩石・地層が削られることを【 ? 】という。
Q. 浸食された土砂は川の流れなどによって【 ? 】される。
Q. 川の流れによって運搬された土砂は、流れが遅くなるところでは【 ? 】する。
Q. 地層・岩石が地表にあらわれている場所を【 ? 】という。
Q. 地層を構成する岩石・土砂の調査などのために、地中に円筒状の穴をあけることを【 ? 】という。
Q. 地層の重なり方を柱状にあらわした断面図を【 ? 】という。
Q. 海面に対して土地の高さが上昇することを【 ? 】という。
Q. 海面に対して土地の高さが下降することを【 ? 】という。
Q. 地層が圧縮、変形され、波形に曲がった状態を【 ? 】という。
Q. 土砂・火山灰・動物の遺がいなどが堆積し固まってできた岩石を【 ? 】という。
Q. 直径2mm以上の岩石の破片が粘土・砂などによって固まった堆積岩を【 ? 】という。
Q. 直径が1/16~2mmの砂粒からできた堆積岩を【 ? 】という。
Q. 直径が1/16mm以下の粒(泥)からできた堆積岩を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は放散虫などの生物の遺がいが主に海底に堆積してできた堆積岩である。
Q. 【 ? 】はサンゴ・貝殻・フズリナの殻などが堆積して押し固められてできた堆積岩で、炭酸カルシウムを主成分とする。
Q. 火山灰などが堆積して押し固められてできた堆積岩を【 ? 】という。
Q. 地層中に残された生物の遺がい・痕跡を【 ? 】という。
Q. 地層が堆積した時代を特定することができる化石を【 ? 】という。
Q. 地層が堆積した環境を特定することができる化石を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は約5億4200万年前から約2億5100万年前までの時代で、三葉虫の存在、最初のセキツイ動物である魚類の出現、シダ植物の繁栄などが特徴である。
Q. 【 ? 】は約2億5100万年前から約6600万年前までの時代で、アンモナイトの存在や恐竜の繁栄などが特徴である。
Q. 【 ? 】は約6600万年前から現在までの時代で、ホニュウ類の繁栄などが特徴である。
気象とその変化
気象観測
Q. 大気の状態や大気中で起こる自然現象を【 ? 】という。
Q. ある地点・時刻での気象状態を【 ? 】という。
Q. 地上1.25~2.0mの大気の温度を【 ? 】という。
Q. 空気がふくむ水蒸気の割合を【 ? 】という。
Q. 空気の重さによって地表が受ける圧力を【 ? 】という。
Q. 乾球・湿球を使い気温・湿度を同時に測定する装置を【 ? 】という。
Q. 天気・気圧・気温などの値を【 ? 】記号や等圧線などを使って地図上にあらわした図を【 ? 】という。
Q. 天気記号と風力記号を組み合わせ、天気・風向・風力・気温・気圧をあらわしたものを【 ? 】という。
霧や雲の発生
Q. 1m3の空気にふくむことのできる最大の水蒸気量を【 ? 】という。
Q. 空気中の水蒸気が凝結して水滴になりはじめるときの温度を【 ? 】という。
Q. 直径0.01mm程の微小な水滴・氷の粒(【 ? 】粒)が大気中に浮かんでいるものを【 ? 】という。
Q. 雲の中で水滴が集まり地上に落下してきたもの、またはその現象を【 ? 】という。
Q. 地表・海面の付近で空気中の水蒸気が凝結し、微小な水滴が浮かぶ状態を【 ? 】という。
Q. 空気中にふくまれている水蒸気が物体にふれることで、その物体を凝結核として水蒸気は水滴となる。この水滴を【 ? 】という。
Q. 大気中の雲粒のうち、氷の結晶が空から落下してくる天気のこと、または氷の結晶を【 ? 】という。
Q. 大気中の水蒸気が雨・雪などとして地上に落下することを【 ? 】という。
前線の通過と天気の変化
Q. 強い上昇気流によって山や塔のように垂直に発達した雲を【 ? 】といい、急な大雨・雷・ひょう・突風などをもたらす。
Q. 空全体を覆う灰色をした厚い雲を【 ? 】といい、穏やかな雨・雪を広範囲に連続的に降らせる。
Q. 広い範囲にわたり気温・水蒸気量がほとんど同じである空気の塊を【 ? 】という。
Q. 異なる気団の間にある境界面を【 ? 】面といい、【 ? 】面が地上と交わる線のことを【 ? 】という。
Q. 周囲と比べて気圧の高い部分を【 ? 】という。
Q. 周囲と比べて気圧の低い部分を【 ? 】という。
Q. 天気図で気圧が等しい地点を結んだ曲線を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は、暖気団の勢力が強く、寒気団に乗り上げながら押して進むときにできる前線である。
Q. 【 ? 】は、寒気団の勢力が強く、暖気団の下にもぐりこみ押し上げながら進むときにできる前線である。
Q. 温帯低気圧にともなう寒冷前線が同様にともなう温暖前線に追いつくと、【 ? 】ができる。
A. へい塞前線 (閉塞前線)
Q. 暖気団と寒気団の勢力がほとんど等しいとき、両気団の境目には【 ? 】ができる。
Q. 日本付近において、6、7月頃にオホーツク海気団と小笠原気団の間にできる停滞前線を【 ? 】という。
Q. 夜間に陸地から海に向かって吹く風を【 ? 】という。
Q. 昼間に海から陸地に向かって吹く風を【 ? 】という。
日本の気象
Q. 【 ? 】は低温で乾燥した寒気団で冬にシベリアの大陸上で発達する。
A. シベリア気団 (シベリア高気圧)
Q. 【 ? 】は寒冷・多湿な寒気団で、春から夏にかけてオホーツク海上で発達する。
A. オホーツク海気団 (オホーツク海高気圧)
Q. 【 ? 】は高温・多湿な暖気団で、夏に日本の南東海上で発達する。
A. 小笠原気団 (小笠原高気圧;太平洋高気圧)
Q. 【 ? 】は乾燥した暖気団で、春と秋に揚子江流域に現れる。また、一部が切り離されて移動性高気圧となり、日本付近を通過する。
A. 揚子江気団 (長江気団)
Q. 【 ? 】は日本付近における典型的な冬型の気圧配置で、西のユーラシア大陸にはシベリア高気圧が発達し、東の海上には低気圧が発達する。
Q. 【 ? 】は日本付近における典型的な夏型の気圧配置で、南に小笠原高気圧が発達し、北に低気圧が発達する。
Q. 東アジアの広範囲の地域において、6、7月頃に雨や曇りの日が続く時期を【 ? 】という。
Q. 熱帯低気圧のうち、北西太平洋または南シナ海に存在し、低気圧域内の最大風速が17.2m/s以上のものを【 ? 】という。
Q. 移動していく高気圧のことを【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は季節によって一定方向に吹く風のことで、モンスーンともいう。
Q. 緯度30~60度付近にかけての中緯度上空では、強い西寄りの風が1年中吹いている。この風を【 ? 】という。
地球と宇宙
日周運動と自転
Q. 地球を中心として、天空に惑星・恒星などが張り付いて運動するように見立てた球体を【 ? 】という。
Q. 恒星・惑星・衛星など、宇宙に存在する物体の総称を【 ? 】という。
Q. 天体が天の子午線を通過することを【 ? 】という。
Q. 天体が南中したときの高度を【 ? 】という。
Q. 天体がそれ自身の軸のまわりを回転することを【 ? 】と言う。
Q. 地球の自転によって、地球上からは天体は東からのぼって西へ沈むように見える。この見かけの運動を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】とは、地球から見た天球上における複数の恒星の配置を、その特徴によって区分したものである。
Q. 天の北極に最も近い明るい星を【 ? 】という。
年周運動と公転
Q. 天体が他の天体のまわりを一定の向きに周期的にまわることを【 ? 】という。
Q. 天体が他の天体を1度公転するのにかかる時間を【 ? 】という。
Q. 太陽の年周運動による天球上での見かけ上の通り道を【 ? 】という。
Q. 太陽が東に昇ることを【 ? 】といい、太陽の上端が東の地平線に接する瞬間が【 ? 】の時刻である。
Q. 太陽が西にしずむことを【 ? 】といい、太陽の上端が西の地平線に接する瞬間が【 ? 】の時刻である。
Q. 太陽が黄道上で最も北の点を通るときを【 ? 】といい、1年のうち太陽の南中高度が最も高く、昼の時間も最も長い。
Q. 太陽が黄道上で最も南の点を通るときを【 ? 】といい、1年のうち太陽の南中高度が最も低く、昼の時間も最も短い。
Q. 太陽が【 ? 】点を通る3月21日ごろを【 ? 】といい、太陽は真東から出て真西に入り、昼夜の長さはほぼ等しい。
Q. 太陽が【 ? 】点を通る9月23日ごろを【 ? 】といい、太陽は真東から出て真西に入り、昼夜の長さはほぼ等しい。
太陽
Q. 【 ? 】は地球から最も近い恒星で、【 ? 】系の中心にある。地球からの距離は約1.5億km。
Q. 太陽の表面に出現する黒い斑点を【 ? 】という。
月の運動と見え方
Q. 新月から約14日が経ち、円形に輝く月を【 ? 】という。
惑星と恒星
Q. 太陽や、太陽を中心としてまわりを公転する天体とその衛星など、太陽の引力の影響下にある集団を【 ? 】という。
Q. 太陽のように、自ら熱・光を発する天体を【 ? 】という。
Q. 恒星のまわり公転する比較的大きな天体を【 ? 】という。
Q. 惑星のまわりを公転する天体を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は太陽系の惑星の1つで、太陽に最も近いところを公転している。
Q. 【 ? 】は太陽系の惑星の1つで、水星と地球の間で太陽のまわりを公転している。
Q. 日の入り後に西の空に見える金星を【 ? 】という。
A. よいの明星 (宵の明星)
Q. 日の出前に東の空に見える金星を【 ? 】という。
Q. 【 ? 】は太陽系にある惑星の1つで、太陽から3番目に近い距離にある。人類などの生物が住んでいる。
Q. 【 ? 】は太陽系にある惑星の1つで、太陽から4番目に近い距離にある。表面は赤褐色をしている。衛星はフォボスとデイモスの2個。
Q. 【 ? 】は太陽系にある惑星の1つで、太陽から5番目に近い距離にある。大きさ・質量ともに太陽系最大。多数の衛星をもつ。
Q. 天文学において、【 ? 】とはあらゆる天体が存在する空間である。
Q. 【 ? 】は黄道12星座の1つで、春に南の空の高いところに見られる。1等星のレグルスが白色に輝く。
Q. 【 ? 】は黄道12星座の1つで、夏に南の空の低いところに見られる。1等星のアンタレスが赤く見える。
Q. 【 ? 】は天の赤道上にある星座で、冬に南の空に見られる。赤色のベテルギウスと白色のリゲルが1等星。