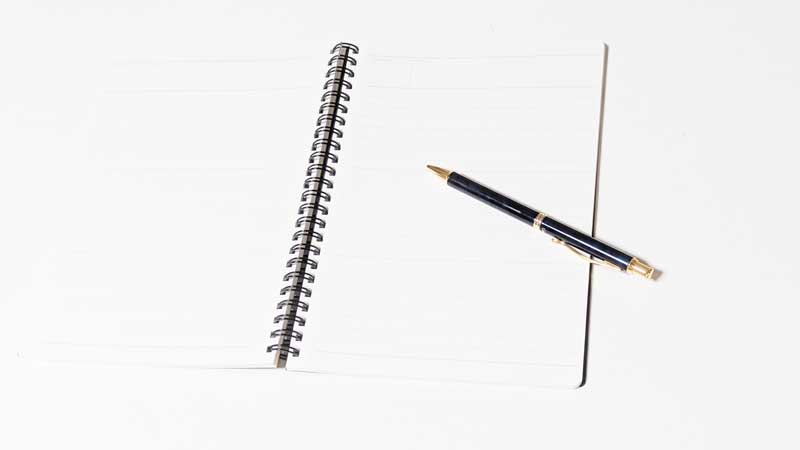身近な物理現象
光の反射・屈折
A.
A.
物体の表面に当たる光を入射光という。
A.
物体の表面で反射した光を反射光という。
A.
A.
透明な物質には空気・水などがある。
A.
屈折した光を屈折光という。
A.
ある角度をこえて全反射がおこるとき、そのある角度を臨界角という。
A.
凸レンズのはたらき
A.
凸レンズは光を1点に集めることができる。中央部がへこんでいるレンズは凹レンズという。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
実像は上下左右が逆になる。
A.
A.
A.
A.
虚像は、物体の向きは同じで、大きく見える。また、スクリーンにうつすことはできない。
音の性質
A.
波は、進行方向と振動方向が同じものを縦波といい、進行方向と振動方向が垂直のものを横波という。縦波は、物質のつまっている部分とそうでない部分ができることから、疎密波ともいう。
A.
音は物体の振動が耳に伝わることで聞こえる。振幅が大きいと音も大きく、振幅が小さいと音も小さい。音の大きさを表す単位はデシベル(dB)。
A.
振動数の単位はヘルツ(Hz)。振動数が多いと音は高くなり、振動数が少ないと音は低くなる。
A.
光の速さは約30万km/s。
A.
力のはたらき
A.
力は大きさと向きをもつ。力の大きさの単位はニュートン(N)やキログラム重(kg重)がある。
A.
ばねの伸びとばねを引く力の大きさは比例する。この法則をフックの法則という。
A.
弾性により生じる力を弾性力という。
A.
A.
A.
A.
+と-は引き合う。+と+、-と-はしりぞけ合う。
A.
A.
重さの単位はニュートン(N)やキログラム重(kg重)。地球・月など、場所によって重さは変化する。
A.
質量の単位はキログラム(kg)やグラム(g)。場所が変わっても質量は変化しない。
A.
圧力
A.
A.
A.
電流とその利用
回路と電流・電圧
A.
A.
A.
A.
A.
A.
電流の単位はアンペア(A)。1Aは1000mA(ミリアンペア)。
A.
電圧の単位はボルト(V)。
A.
電池や電源装置など。
A.
A.
電源装置は電圧を変えることができる。また、途中で電圧が下がることもなく、一定に保つことができる。
A.
A.
発光ダイオードはLEDともいう。消費電力が少なく、発熱が少ない。電球よりも寿命が長い。
A.
A.
A.
A.
A.
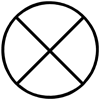
A.
A.
A.
抵抗器のうち、本問のものは固定抵抗器。
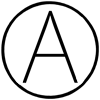
A.
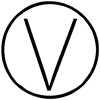
A.
A.
A.
電流・電圧と抵抗
A.
電気抵抗の単位はオーム(Ω)。
A.
A.
電圧をV(V)、電流をI(A)、電気抵抗をR(Ω)とすると、V = I × R が成り立つ。
電気とそのエネルギー
A.
仕事とは、物体の移動・発熱・発光などのこと。電力の単位はワット(W)。電力をP(W)、電圧をV(V)、電流をI(A)とすると、P = V × I であらわされる。
A.
電力量の単位はジュール(J)。電力量をW(J)、電力をP(W)、時間をt(秒)とすると、W = P × t が成り立つ。電力会社などは電力量をkWh(キロワット時)で表すこともある。
A.
熱量の単位はジュール(J)やカロリー(cal)が用いられる。
A.
ジュール熱(熱量)をQ(J)、電圧をV(V)、電流をI(A)、時間をt(秒)とすると、Q = V × I × t が成り立つ。また、電力をP(W)とすると、P = V × I なので、Q = P × t ともいえる。
静電気と電流
A.
摩擦で生じる静電気は特に摩擦電気という。静電気には+と-の2種類があり、物質によってどちらの電気を帯びやすいかが異なる。
A.
雷は雲と雲・大地などの間でおこる放電である。
A.
真空放電管ともいう。高い電圧をかけると真空放電を行う。
A.
陰極線ともいう。
A.
A.
電流がつくる磁界
A.
磁場ともいう。磁気とは、磁石などにはたらく、引き合ったりしりぞけ合ったりする力の源のことである。
A.
磁石のまわりでは、磁界はN極から出てS極に向かう。
A.
A.
A.
A.
A.
コイルでは、中心を貫く強い磁界ができる。その磁界の向きは、右手でコイルを握ったとき、人差し指から小指までの指先の向きを導線に流れる電流の向きに合わせた場合、親指を伸ばした向きになる。
A.
A.
方位磁針ともいう。
磁界中の電流が受ける力
A.
電磁誘導と発電
A.
A.
A.
検流計の+端子に電流が流れ込む場合、指針は右に振れる。逆に-端子に電流が流れ込む場合は、指針は左に振れる。
A.
A.
直流電流ともいう。
A.
交流電流ともいう。
運動とエネルギー
力のつり合い
A.
A.
A.
A.
運動の速さと向き
A.
速さの単位はメートル毎秒(m/s)やキロメートル毎時(km/h)など。移動の方向を考える場合は速度という。速度の大きさは速さに等しい。
A.
記録タイマーは交流の周波数に合わせて打点する。東日本では1/50秒ごとに、西日本では1/60秒ごとに打点する。そのため、東日本では5打点間の距離を、西日本では6打点間の距離を測定することで、0.1秒間に進んだ距離を求めることができる。
A.
ある瞬間における速さを瞬間の速さという。
A.
力と運動
A.
A.
A.
A.
A.
A.
仕事とエネルギー
A.
A.
仕事率の単位はワット(W)や1kg重m/sなどで表される。1(W) = 1(J) ÷ 1(s)。1(kg重m/s) = 1(kg重m) ÷ 1(s)。
A.
回転の中心を支点、てこに力を加える点を力点、物体に力をはたらかせる点を作用点という。
A.
斜面を使う場合は力を加え続ける距離が長くなるので、直接持ち上げる場合と仕事の量は同じになる。実際には摩擦の影響で斜面を使う場合の方が必要な仕事の量が増えてしまうが、ここではそれを無視して考えている。
A.
仕事の原理について考える場合は、通常、斜面との摩擦や滑車の質量などは無視して考える。
A.
エネルギーの単位はジュール(J)。
A.
A.
A.
A.
例えば、2mの位置にある物体と、そこから自由落下して1mの位置にある物体の力学的エネルギーは等しい。2mの位置にある場合は運動エネルギーはゼロである。一方、1mの位置に落下すると位置エネルギーは減少するが、運動エネルギーはその分増加する。
科学技術と人間
さまざまなエネルギーとその変換
A.
運動エネルギーの一部は、摩擦力により熱エネルギーにかわる。
A.
太陽光発電や植物の光合成などで利用されている。
A.
モーターは電気エネルギーを運動エネルギーにかえている。
A.
電池は化学反応によって化学エネルギーを直流の電流にかえている。
A.
エネルギー資源
A.
A.
A.
A.
水は流れるとき、位置エネルギーが運動エネルギーにかわる。水力発電では、その水の運動エネルギーを利用して、電気エネルギーを得ている。
A.
A.
主に水素と酸素が使われる。
A.
A.
A.
α線・β線・γ線・X線などがある。