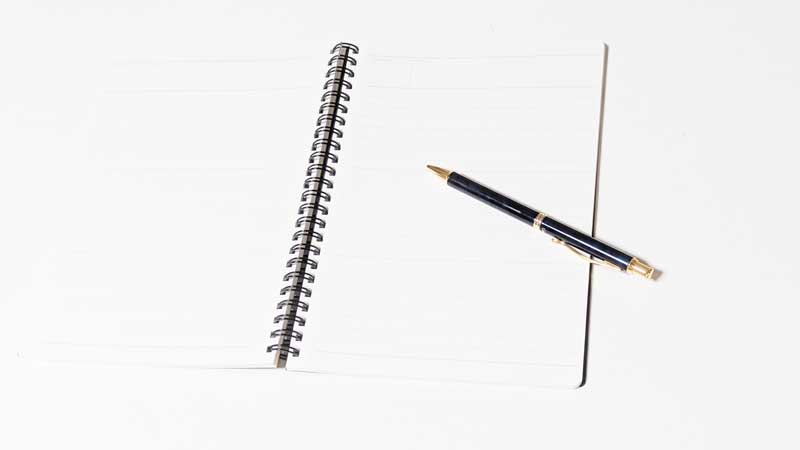時代区分
年代の数え方
A.
紀元元年以降を明示する場合はA.D.やADと表記される。イエスが生まれる前は紀元前といい、(紀元)前やB.C.、BCと表記される。例えば紀元元年の次の年は「2年」や「A.D.2年」、紀元元年の前の年は「前1年」や「B.C.1年」となる。
A.
1世紀は西暦1~100年、2世紀は西暦201~300年、3世紀は301~400年。
時代区分
A.
諸説ある。
A.
諸説ある。
A.
諸説ある。
A.
A.
A.
人類の進化
人類の誕生
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
旧石器時代と新石器時代
A.
猿人は簡単な打製石器を使用していた。
A.
A.
A.
A.
日本では縄文時代にあたる。
A.
A.
A.
世界の古代文明や宗教のおこり
世界の古代文明
A.
A.
A.
A.
パピルスは植物の繊維で作られた一種の紙。
A.
A.
A.
A.
A.
太陰暦は「たいいんれき」と読む。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
儒教は、政治や道徳を説いた、思想や教学の総称である。
A.
A.
現存する万里の長城は、大部分が明代につくられた。
A.
漢は「かん」と読む。
A.
ポリスにはアテネやスパルタなどがある。
A.
ローマ帝国は紀元前8世紀頃のイタリアの都市国家が起源。
A.
宗教のおこり
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
古代までの日本
縄文文化
A.
縄文土器には縄目の文様がないものも多い。縄文土器が使われた約1万年前の時代を縄文時代といい、その文化を縄文文化という。
A.
A.
A.
土偶は女性をかたどったものが多く、多産や豊穣、繁栄などを祈ってつくられたとされる。
A.
A.
A.
弥生文化
A.
弥生土器が使われた紀元前4世紀頃から紀元3世紀頃までの時代を弥生時代といい、その文化を弥生文化という。
A.
環濠集落とは、周囲に堀をめぐらせた集落のこと。
A.
A.
A.
A.
『漢書』地理志には、紀元前1世紀の倭の様子が書かれている。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
ヤマト王権と古墳文化
A.
古墳は3世紀頃からつくられ始めた。
A.
方形とは四角形のこと。
A.
大仙古墳は仁徳天皇陵とされ、5世紀頃につくられた。陵とは、天皇や皇后などの墓を意味する。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
百済は6世紀に日本に仏教を伝えた。
A.
7世紀には新羅は百済と高句麗を滅ぼし、朝鮮半島を統一した。
A.
加耶は加羅または任那ともいう。
A.
A.
倭の五王は讃、珍、済、興、武の5人をいう。
A.
武は雄略天皇であると考えられている。稲荷山古墳出土鉄剣は、現在の埼玉県にある稲荷山古墳から発見された。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
漢字や儒教、仏教などが伝えられた。
A.
A.
推古朝の政治と飛鳥文化
A.
A.
科挙は598年(隋の時代)に始まり、1905年(清の時代)まで行われた。
A.
唐は907年まで続いた。
A.
A.
推古天皇は史上初の女性の天皇であった。
A.
聖徳太子は、厩戸王の後世の呼称である。
A.
A.
冠位十二階の制度では、徳、仁、礼、信、義、智を大小に分け(大徳、小徳、大礼など)て12階位とされ、氏(血縁関係にある集団)ではなく個人に与えられた。
A.
憲法十七条ともいう。仏法僧とは、仏と法と僧のこと。
A.
A.
A.
A.
A.
大化の改新
A.
A.
中臣鎌足は亡くなる際に、天智天皇に藤原の姓を賜ったため、藤原鎌足ともいう。
A.
A.
A.
大化の改新は唐の律令制を基にした政治改革である。
A.
A.
中大兄皇子は、667年に近江大津宮に遷都し、668年に即位するまでは、称制という形で政治を行っていた。称制とは、即位せずに政治を行うこと。
A.
676年に新羅が朝鮮半島を統一した。
A.
天智天皇の子が大海人皇子で、弟が大友皇子。
A.
A.
奈良時代の政治・社会と天平文化
A.
令は701年に施行され、律は702年に施行された。
A.
A.
A.
A.
五畿は大和・山背(山城)・摂津・河内・和泉の5か国で、まとめて畿内という。七道は東山道・北陸道・東海道・山陰道・山陽道・南海道・西海道をいう。
A.
A.
人々は良民と賤民に大別された。口分田は、良民の男には2反(1反=360歩)、良民の女には3分の1を減らして1反120歩が与えられた。賤民にはその種類によって、与えられる口分田の広さが変わった。
A.
A.
708年の和同開珎は最も古い流通貨幣。
A.
平城京は、唐の長安を手本としてつくられた。平城京に都が置かれた時代を奈良時代という。
A.
約3%というのは、当時の単位でいうと、田1段の公定収穫量72束につき2束2把。
A.
A.
庸は調とともに都へ運ばれた。
A.
A.
A.
A.
既存のかんがい施設をつかって開墾した場合は、1世代のみ土地を所有できた。
A.
墾田永年私財法により、貴族・地方豪族・神社・寺院は浮浪人を集めて大規模に開墾を進めていった。こうして私的所有地が増え、公地公民制が崩れていった。
A.
A.
A.
A.
A.
行基という僧が大仏造立に協力した。大仏は752年に開眼供養が行われ、完成した。高さは約16m。
A.
A.
A.
『古事記』は7世紀後半に天武天皇が編纂を命じた。
A.
A.
編年体とは、年月の順に事実を記述する書き方。『日本書紀』は7世紀後半に天武天皇が編纂を命じた。
A.
『万葉集』巻5に収められている。
A.
A.
平安時代の政治・社会と国風文化
A.
A.
794年から鎌倉幕府成立までの約400年間を平安時代という。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
藤原道長以来の約60年が摂関政治の最盛期。
A.
奈良時代の743年に出された墾田永年私財法により、貴族や寺社は浮浪人を集めて大規模に開墾を進めていった。こうして私的所有地が増え、公地公民制が崩れていったことが、荘園の発達につながった。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
定子は藤原道隆の長女。定子は中宮だったが、後に皇后となった。
A.
A.
彰子が中宮となることで、定子は中宮から皇后となった。
A.
A.
A.
A.
A.
武士の台頭、院政と平氏政権
A.
反乱は940年に鎮圧された。反乱を起こした勢力も、鎮圧した勢力も武士であった。
A.
反乱を起こした勢力も、鎮圧した勢力も武士であった。平将門の乱と藤原純友の乱を総称して、承平・天慶の乱ともいう。
A.
惣領は一族の長。家子は惣領の分家など。郎党は上級武士に従う下級の兵士。
A.
前九年合戦ともいう。
A.
後三年合戦ともいう。
A.
A.
平泉は岩手県にある。
A.
A.
A.
後白河天皇側が反撃し、半日で勝利した。
A.
A.
平氏は、太政大臣や天皇の外戚(母方の親戚)という地位についていたり、荘園などに経済基盤があったりと、貴族化していた。
A.
大輪田泊は今の神戸港のこと。宋は当時の中国にある王朝の1つ。
A.
令旨とは、皇太子や親王などの命令を伝える文書のこと。後白河法皇は平氏によって幽閉されていた。
A.
A.
中世
鎌倉時代の政治・社会・産業・経済
A.
鎌倉幕府の確立は、源頼朝が守護・地頭を設置する権限を手に入れた1185年とする説や、征夷大将軍に任命された1192年とする説などがある。
A.
A.
A.
A.
領地については、本領安堵(領地を認めること)や新恩給与(領地を与えること)という。
A.
A.
A.
A.
公文所は政所に吸収された。
A.
A.
A.
A.
北条政子が東国の御家人に対して源頼朝の御恩を訴え、大半が幕府軍となった。その結果、戦いは幕府軍が勝利した。
A.
六波羅探題は京都の六波羅におかれた。
A.
御成敗式目は武家社会での最初の成文法(文章化された法律)。
A.
A.
A.
A.
A.
犂というすきが使われた。
A.
A.
夏には米、冬には麦を栽培するなど。
A.
A.
問ともいう。室町時代には問屋へと発展した。
A.
日宋貿易が行われていたが、日本と宋の間には正式な国交はなかった。
元の襲来と鎌倉幕府の動揺
A.
A.
A.
A.
マルコ=ポーロはイタリアのベネチアに生まれた商人・探検家。
A.
『世界の記述』(または『東方見聞録』)で日本はジパングと呼ばれ、黄金が無尽蔵にあるらしいと紹介されていた。
A.
元軍の集団戦法・「てつはう」などの火器の利用・毒矢などに、日本の武士は苦しんだ。
A.
A.
蒙古襲来ともいう。元寇では防衛戦で戦利品がなかったため、御家人は奉公に対しての恩賞をもらえず、幕府への不満がつのった。
A.
A.
元寇に対する負担によって、生活が更に苦しくなった。
A.
A.
A.
1333年に隠岐を脱出。
A.
足利尊氏はもともと執権北条高時から「高」の字を賜り足利高氏と名乗っていたが、後に後醍醐天皇の名前から「尊」の字を賜り、尊氏に改名した。
A.
鎌倉幕府が崩壊した基本的な要因は、北条氏の惣領(一族の長)である得宗の専制政治に対して、不満が高まったことにある。
鎌倉仏教
A.
一心に「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば誰もが救われると説いた。
A.
悪人正機説を唱えた。
A.
一遍は踊りながら念仏を唱える踊念仏を始めた。
A.
「南無妙法蓮華経」という題目を唱えることで救われると説いた。
A.
臨済宗は禅宗の1つの宗派で、坐禅により自力の修行で悟りをひらくと説いた。
A.
曹洞宗も禅宗の1つの宗派。ひたすら坐禅することで悟りはひらかれると説いた。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
鎌倉文化
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
琵琶法師は琵琶を弾きながら語った。
A.
力強さや写実性、人間味が特徴。
A.
A.
A.
A.
A.
『蒙古襲来絵巻』ともいう。
南北朝の内乱と室町時代の政治・社会
A.
A.
吉野は現在の奈良県にある。
A.
A.
南北朝の内乱ともいう。
A.
1336年に足利尊氏が建武式目を制定した時点で、すでに幕府としての政治は始まっていた。
A.
A.
A.
A.
鎌倉府は鎌倉におかれた。
A.
A.
A.
時期によって、前期倭寇と後期倭寇にわけられる。前期倭寇は主に日本人であったが、後期倭寇には日本人は少なかった。
A.
日本は刀剣・銅・硫黄などを輸出し、明から明銭(銅銭)・生糸・絹織物などを輸入した。
A.
A.
琉球王国の前には、北山・中山・南山という3つの国があった。
A.
A.
A.
A.
A.
土倉は土壁のくらを持っていたことから呼ばれた。酒屋は醸造業者で、土倉を兼ねることもあった。
A.
民衆の反抗、戦国大名の成立
A.
または惣村という。畿内近国で組織された。
A.
A.
正長の土一揆ともいう。
A.
応仁の乱により、幕府の権威は失墜した。
A.
戦法が、これまでの騎兵による個人戦から、歩兵の集団戦へと変化した。
A.
応仁の乱以降、国人(武士)と農民が守護大名である畠山氏の内紛による被害をうけていたことが原因。この一揆の結果、36人の月行事による自治が8年間続いた。
A.
この一揆により地域は本願寺の領国となり、約100年間、坊主・国人(武士)・農民による自治が続いた。
A.
A.
A.
A.
室町文化
A.
舎利電は釈迦の遺骨を安置した建物。邸宅は足利義満の死後、鹿苑寺となった。
A.
A.
A.
山荘は足利義政の死後、慈照寺となった。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
町衆は「まちしゅう」とも読む。
近世
ヨーロッパ人の来航
A.
ルネサンスはフランス語で「再生」を意味する。
A.
A.
A.
プロテスタントとは「抗議する者」という意味。ルター派がその宗派を禁止されたことに対して行った抗議に由来する。
A.
A.
西インド諸島とは、南北アメリカ大陸の間にある島々のこと。コロンブスは地球球体説に基づき、大西洋を西へ進めばアジアに到達できると考えていた。
A.
A.
マゼランはフィリピンでラプラプに殺された。世界一周はマゼランの部下18名が達成した。
A.
A.
A.
A.
A.
南蛮貿易では中国産の生糸が多く輸入された。他にも、鉄砲や皮革(動物の皮)が輸入されている。輸出品は銀や刀剣などがあった。
A.
肥前は現在の長崎県・佐賀県の辺りに位置する。
A.
フランシスコ=ザビエルは鹿児島にやって来た。
A.
織田信長と豊臣秀吉の全国統一
A.
A.
その後、足利義昭は浅井長政や朝倉義景、比叡山延暦寺と結び、織田信長に対抗した。しかし、織田信長は1570年に姉川の戦いで浅井・朝倉の連合軍を破り、1571年には比叡山延暦寺を焼き打ちにした。そして1573年、織田信長は足利義昭を追放して室町幕府を滅ぼした。
A.
A.
その後、1580年、織田信長は石山本願寺を屈服させた。
A.
この出来事を「本能寺の変」という。
A.
座とは、商工業者の同業組合のこと。
A.
秀吉は石山本願寺の跡地に大坂城を築き、全国統一の本拠地とした。
A.
A.
検地とは土地調査のことである。これまでは1つの土地に複数人の所有権が重なっていたが、太閤検地によって、直接の耕作者1人が所有権を持てるよう保証された。その耕作者は検地帳に記された。
A.
豊臣秀吉は、農民が一揆をおこさないようにするために、刀狩を行った。
A.
兵農分離により、武士・町人・農民の身分が分離され、武士が町人や農民になったり、農民が商売を行ったりすること等が禁止された。このことが江戸時代の士農工商という身分制度につながっていく。
A.
一方で南蛮貿易は奨励されたため、キリスト教の禁止は徹底されていなかった。
A.
2度の出兵のうち、1592年の出兵を文禄の役、1597年の出兵を慶長の役という。これらを2つ合わせて文禄・慶長の役、または朝鮮出兵ともいう。この出兵が大名や民衆の大きな負担となり、豊臣政権の統制が弱まった。
桃山文化
A.
中世には仏教文化が栄えたが、安土桃山時代には豪華で壮大な文化が生み出された。桃山文化は城郭に代表される豪華な文化、大商人の財力を背景とした現実的で人間的な文化、南蛮文化を特徴とする。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
南蛮文化は桃山文化を支える特色の1つである。活版印刷術・医学・天文学・地理学などが日本に伝わった。また、現代でもなじみのあるパン・カステラ・タバコなどはポルトガル語で、桃山文化の時代に伝わった。
江戸幕府の成立と政治・社会
A.
A.
結果は東軍が勝利し、徳川家康の覇権が確立した。
A.
A.
A.
A.
親藩や譜代大名は、関東・近畿・東海道沿いなどの要地に置かれた。
A.
外様大名は要職にはつけず、東北や九州などの辺境に置かれた。
A.
臨時に設けられる大老が最高の役職である。
A.
武家諸法度は将軍が替わるごとに出された。
A.
参勤交代によって、大名は妻子を人質として江戸に住まわせ、国元(領地)と江戸を1年交代で往復した。家康の頃から大名が自発的に行っていたものを、家光が制度化した。
A.
A.
A.
A.
本百姓は四公六民(収穫高の4割)や五公五民(収穫高の5割)を年貢として領主に納めた。
A.
小作とは、地主から土地を借りて、その土地を耕作して農業を営むことをいう。
A.
17世紀前半の貿易・対外関係
A.
A.
輸出品は銀が多く、輸入品は中国の生糸が多かった。生糸の輸入では、江戸幕府は糸割符制度をつくり、特定の商人に生糸を一括で購入させ、輸入価格を下げさせた。
A.
日本町には日本人がまとまって住み、自治制がとられた。
A.
A.
翌年1613年には禁教令を全国におよぼした。江戸幕府は、キリスト教徒が団結して一揆を起こすことや、スペイン・ポルトガルが日本を植民地化しに攻めてくることを恐れていた。
A.
A.
江戸幕府はキリスト教を恐れており、島原の乱を経験することで、キリスト教に対して更に危機感を持った。
A.
朝鮮・琉球・アイヌとは引き続き交流があった。
A.
貿易港は長崎だけに制限された。
A.
A.
A.
豊臣秀吉の出兵によって朝鮮とは国交を断絶していたが、徳川家康は対馬(長崎県)の宗氏を通じて朝鮮との国交再開を打診した。通信使は最初の3回は回答兼刷還使と称し、朝鮮から連行された人々を連れ帰った。その後、通信使は将軍の代替わりごとに来日した。
A.
島津氏は琉球に中国(明、続いて清)との朝貢貿易を続けさせ、大きな利益を得ていた。琉球は幕府から使節の派遣を強制され、将軍の代替わりごとに慶賀使を、琉球国王の代替わりごとに謝恩使を江戸まで派遣した。
A.
蝦夷地(北海道)では、1457年、蠣崎氏(後の松前氏)がコシャマインの反乱を鎮圧した。その後、アイヌに不利な交易を行ったため、1669年、シャクシャインの反乱がおこった。
産業・交通・都市の発達
A.
新田の種類だけではなく、農業技術も改良された。農具には、田畑を深く耕すための備中鍬、脱穀には千歯扱き、籾殻やごみを飛ばし穀物を選別する唐箕や千石簁などが利用された。
A.
金肥は元禄期の頃(16世紀末頃)から使用されるようになった。金肥には干鰯・油粕などが利用された。
A.
百姓は商品作物を販売し、貨幣を獲得した。商品作物には四木(茶・桑・楮・漆・三草(藍・麻・紅花)が主に栽培された。
A.
綿織物業や絹織物業において、18世紀に広まった。
A.
A.
五街道は江戸の日本橋を起点とする幹線道路。脇街道はその他の街道。五街道は東海道・中山道・甲州道中・日光道中・奥州道中の5つをいう。
A.
関所の通行には関所手形が必要。特に、江戸に鉄砲が入ることや、江戸から大名の妻子が逃亡することを、「入鉄砲に出女」として厳しく取り締まった。
A.
物資を大量に輸送するために、水上交通網が発達した。東北の日本海沿岸から下関経由で大坂(大阪)に至る航路を西廻り航路という。江戸・大坂間の航路は南海路といい、菱垣廻船・樽廻船という定期船が往復した。大坂・長崎間は西海路といい、舶来物とよばれた長崎貿易による輸入品が大坂に運ばれた。
A.
「大坂」は明治初年に「大阪」に改められた。
A.
A.
蔵屋敷は大坂(大阪)に最も多い。
A.
株仲間は8代将軍吉宗の時に公認された。江戸幕府は株仲間に営業の独占を認めるかわりに、運上・冥加という営業税をとった。
A.
17世紀後半~18世紀後半の政治・社会
A.
A.
A.
1680~1709年在職。徳川綱吉は文治政治(武力によらない政治)を行った。1657年の明暦の大火による江戸市街の復興に多額の費用を要していたため、徳川綱吉の頃にはすでに財政は厳しかった。更に、綱吉の華美な生活や、仏教信仰による寺社の造営費用などのために、財政は悪化していった。
A.
A.
A.
新井白石が進めた文治政治(武力によらない政治)を正徳の治という。新井白石は、物価の高騰を抑制するために貨幣の改鋳を行ったり、金・銀の流出を防ぐために長崎貿易を制限したりした。
A.
1716~1745年在職。
A.
享保の改革では、家康の時代の政治を目指した。将軍権力の強化や、財政の再建のために質素倹約の励行・農村の振興などを行った。
A.
A.
享保の改革の政策の1つ。上げ米の制を実施するにあたり、参勤交代をゆるめて、江戸にいる期間を半分にした。また、年貢を増やすために、検見法(毎年の収穫状況による)から定免法(毎年一定額)へ変更したり、年貢率を四公六民から五公五民へ引き上げたりした。
A.
A.
A.
藩校は藩学ともいう。藩士とは大名の家臣のこと。
A.
田沼意次は商人資本を利用する政策をとったが、最終的には賄賂政治によって不評を買い、1786年に失脚した。その頃、天明の飢饉や浅間山の大噴火などで、民衆の生活は困窮していた。
A.
他にも、金・銀を手に入れるために長崎貿易を奨励し、銅や俵物(干した海産物を俵に詰めたもの)を中国に輸出した。また、新田開発のために印旛沼・手賀沼の干拓にも着手したが、これは災害のため失敗した。
A.
A.
A.
寛政の改革では、農村復興に重点を置いた政策をとった。また、都市・経済政策としては、貧しい人を救うために七分積金の制度を実施したり、軽罪を犯した無宿者に職業訓練を行う人足寄場を設けたりした。
A.
棄捐令は寛政の改革による政策の1つ。札差とは、旗本・御家人に支給される米を仲介する者で、金貸しも行っていた。
A.
旧里帰農令は寛政の改革による政策の1つ。
A.
1797年、聖堂学問所は昌平坂学問所(昌平黌)となった。
A.
ラクスマンの要求は拒否されたため、ラクスマンは長崎入港許可証を受け取り帰国した。
19世紀前半の政治・社会
A.
外国船打払令または無二念打払令ともいう。
A.
各地で百姓一揆や打ちこわしがおこった。
A.
この反乱を大塩の乱という。
A.
A.
享保の改革・寛政の改革を模範とした。厳しい倹約令を出し、ぜいたく品や華美な衣服などを禁止することで、農村復興と財政再建をはかった。
A.
水野忠邦は物価の上昇について、株仲間が市場を独占することによって自由競争が行われないためであると考えた。
A.
幕府は、1840~42年のアヘン戦争で清がイギリスに敗れたことを知り、外国との戦争を避けることにした。薪水給与令(文化の薪水給与令 / 文化の憮恤令)は1806年に一度出されているが、1825年に異国船打払令が出されたことにより、廃止されていた。
A.
天保の改革の政策の1つ。寛政の改革の旧里帰農令はあくまで農民の帰農を「奨励」するものであったが、人返しの法では「強制」となった。
A.
天保の改革の政策の1つ。これにより、水野忠邦は大名・旗本の反対にあい失脚し、天保の改革も挫折した。
A.
A.
モリソン号事件とは、アメリカ船モリソン号が漂流民の返還と通商の交渉のために来航した際、異国船打払令により、浦賀(神奈川県)と山川(鹿児島県)で撃退された事件のこと。
A.
モリソン号事件とは、アメリカ船モリソン号が漂流民の返還と通商の交渉のために来航した際、異国船打払令により、浦賀(神奈川県)と山川(鹿児島県)で撃退された事件のこと。
学問の発達・元禄文化(17世紀後半~18世紀初頭)
A.
A.
紀伝体とは、人物ごとに出来事をに書いていく方式をいう。一方、年代ごとに出来事を並べて書く方式を編年体という。
A.
A.
井原西鶴の代表作は『好色一代男』・『日本永代蔵』・『世間胸算用』などがある。
A.
A.
近松門左衛門の代表作は『曽根崎心中』・『国性爺合戦(国姓爺合戦)』などがある。
A.
松尾芭蕉の代表作は紀行文の『おくのほそ道』が有名。
A.
菱川師宣は美人・役者などを描いた。
A.
浮世絵とは庶民的な風俗画(日常生活を主題とした絵画かいが)のことをいう。
学問の形成と発展・化政文化(19世紀前半)
A.
A.
8代将軍徳川吉宗が実学(実用的な学問)を奨励し、キリスト教に関係のない漢訳洋書の輸入制限を緩めたことが、蘭学の発展につながった。
A.
オランダ語で書かれた『ターヘル・アナトミア』も、ドイツの『解剖図譜』を翻訳したもの。
A.
A.
A.
A.
A.
『古事記』とは、天武天皇が編纂を命じて、712年に完成した日本最古の歴史書である。
A.
化政文化は江戸時代の文化・文政時代を中心に発達した。
A.
A.
これにより浮世絵は全盛期を迎えた。
A.
A.
A.
安藤広重ともいう。
近代
欧米諸国における市民革命
A.
A.
A.
ピューリタン革命ともいう。清教徒(ピューリタン)とは、イングランド国教会に対立したキリスト教のプロテスタント(カルヴァン派)のこと。クロムウェルらの清教徒を中心とする人々が、1649年に国王のチャールズ1世を処刑し、議会による共和制(国王などの君主をおかない政治体制)へと移行した。
A.
清教徒革命(ピューリタン革命)により共和制に移行したが、その後王政が復活した(王政復古)。しかし、それに対して名誉革命がおこり、議会はオランダからメアリー(メアリー2世)とその夫オラニエ公ウィレム(ウィリアム3世)を迎え、2人は共同で王位についた。旧国王のジェームズ2世はフランスに亡命した。
A.
内容は、議会の同意しない課税・逮捕・裁判・法律制定などを禁止するというもの。議会の王権に対する優位が示されている。
A.
A.
ロックは、人間は生まれながらにして自由で平等な権利を持っていると主張した。
A.
モンテスキューは三権分立により、権力の集中を防ぎ、独裁を制限することを主張した。
A.
A.
単に「独立戦争」、または「アメリカ独立革命」ともいう。
A.
1789年、ワシントンはアメリカ合衆国初代大統領となった。
A.
単に「独立宣言」ともいう。イギリスのロックの影響を受けた。1783年には、アメリカとイギリスの間でパリ条約が結ばれ、アメリカは正式に独立が認められた。そして1787年には、アメリカ合衆国憲法が制定された。
A.
A.
A.
当時の人口の98%を占める。
A.
フランス革命は1789~99年の間続いたとされる。この革命によって絶対王政が倒れた。
A.
A.
ナポレオンは1804年に皇帝に即位。ナポレオンによる軍事独裁政権は勢力を拡大し、ヨーロッパのほとんどを勢力下においた。しかし、ロシア遠征の失敗をきっかけに、ヨーロッパ諸国に追い詰められた。そして、ナポレオンは1814年に退位させられ、エルバ島に流された。
欧米諸国における産業革命と資本主義
A.
A.
つまり、手工業による小規模な生産から、機械を用いた大量生産へと発展した。そして、社会構造が変化し、資本主義経済体制へと移行した。
A.
産業革命により資本主義社会が形成された。
A.
資本主義が進展するにつれ、少数の資本家と大多数の労働者の間で貧富の差が生まれ、労働者の生活が困窮した。
A.
1848年革命ともいう。ウィーン体制とは、ヨーロッパをフランス革命以前の状態に戻すという体制で、自由主義やナショナリズムを抑圧していた。
A.
南部はプランテーションによる綿花栽培などの農業が盛んで、ヨーロッパへの輸出に有利な自由貿易を求めていた。また、その労働力として、黒人奴隷が使われていた。北部は工業化が進み、ヨーロッパからの安い輸入品を制限する保護貿易を求めていた。また、人道的な立場から、奴隷制には反対していた。
A.
1861~65年在任。
A.
A.
A.
プロイセンとは、ドイツ統一前における構成国の1つ。ドイツ統一後はプロイセン国王が皇帝を世襲した。
A.
1871年、ドイツは統一され、ドイツ帝国が成立した。
欧米諸国のアジア進出
A.
シパーヒーとは、イギリスが植民地支配のために雇用したインド人傭兵のこと。
A.
東インド会社はインド大反乱の責任を問われ、解散させられた。その後は、イギリスがインドを直接統治することになった。
A.
A.
イギリスは中国から茶を輸入しており、大量の銀が流出した。そこで、イギリスはインドでアヘンを栽培して中国へ密輸し、中国からは茶を輸入することにした。その結果、逆に中国の銀が国外に流出することになった。
A.
A.
A.
南京条約は清にとって不平等なもので、上海をはじめとする5港の開港や香港の割譲、多額の賠償金の支払いなどをすることとなった。また、その後追加で、領事裁判権・関税自主権・片務的最恵国待遇などについても、清に不平等な条約が結ばれた。
A.
日本の開国
A.
A.
日米和親条約の主な内容としては、下田(静岡県)と箱館(函館)(北海道)の2港を開港、アメリカ船に燃料・水・食料を供給、アメリカ領事の下田駐在、アメリカの最恵国待遇などがある。また、同じような条約をイギリス・ロシア・オランダとも結んだ。
A.
A.
日米修好通商条約の内容は、箱館(函館)・神奈川・長崎・新潟・兵庫を開港、領事裁判権を認めること、関税自主権がないことなど。日本にとって不平等な条約であった。また、日本はオランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同じような条約を結んだ。
A.
治外法権ともいう。
A.
A.
A.
A.
吉田松陰や橋本佐内らが死罪にされた。
A.
A.
天皇を敬う思想を尊王論、外国人を排除しようとする思想を攘夷論という。また、尊王攘夷論による運動を尊王攘夷運動という。
A.
生麦事件とは、1862年に薩摩藩の島津久光らが江戸から帰る途中、横浜郊外の生麦でイギリス人3人を殺傷した事件。
A.
A.
薩長同盟は、倒幕(幕府を倒すこと)のための軍事同盟である。
A.
A.
A.
A.
江戸幕府を廃絶し、政治への参加をできないようにした。また、摂政・関白を廃止し、新たに総裁・議定・参与の三職を設置するなどした。
A.
A.
鳥羽・伏見の戦いの後、江戸城の無血開城(幕府が江戸城を血を流すことなく明け渡したこと)を経て、1869年に箱館(函館)(北海道)の五稜郭で旧幕府勢力を降伏させた。
明治政府による政策・改革と文明開化
A.
A.
この頃、年号を明治に改め、一世一元の制という、天皇が1代の間に元号は1つのみとする制度が定められた。また、江戸を東京に、大坂を大阪に改めたりした。首都についても、正式な発表は無かったが、天皇が京都から東京へ移ったことから、実質的に東京が首都となった。
A.
版籍奉還は大久保利通や木戸孝允らの提案によるもの。
A.
その後すぐ3府72県となり、1888年には3府43県となった。
A.
華族とは公卿・大名のことで、士族は旧幕臣・旧藩士、平民は農民・町民のこと。平民が苗字を名のることや、平民と華族・士族の間での結婚、職業選択の自由などが認められた。
A.
身分解放令ともいう。
A.
岩倉具視を大使として、大久保利通・木戸孝允・伊藤博文なども参加した。
A.
日清修好条規は、領事の駐在と領事裁判権を相互に認めた点で、初めて対等な立場で結ばれた条約。
A.
樺太はロシア領、千島を日本領とした。
A.
A.
日朝修好条規は、1875年の江華島事件を口実に結ばれた。江華島事件とは、朝鮮の江華島で、朝鮮が日本軍の挑発行為に対して砲撃したため、日本軍が報復として永宗城島を占領した事件。
A.
この戦争は政府軍が鎮圧した。
A.
北海道の開拓とロシアに対する警備を兼ねた農兵を、屯田兵という。
A.
琉球王国は、1871年に鹿児島県に編入、1872年に琉球藩が設置され、1879年に沖縄県が設置された。これにより琉球処分が完成した。
A.
A.
A.
国民皆学が宣言され、6歳以上のすべての男女に学校教育を受けさせることになった。小学校が義務教育になった。
A.
地券の所有者(土地所有者)が、地価の3%を租税として、現金で納めることになった。後に地租改正反対一揆がおこり、1877年に税率が2.5%に減額された。
A.
地券とは、土地所有権の確認証のこと。
A.
官営模範工場は、群馬県の富岡製糸場が代表的。
A.
A.
A.
A.
街ではガス灯・人力車・鉄道馬車(レールの上を走る馬車)が見られた。髪型も、散髪令によりちょんまげを切り、ざんぎり頭が流行った。暦も太陰暦から太陽暦に改められた。
A.
A.
自由民権運動のおこりと立憲国家の成立
A.
A.
愛国公党が解散後、1874年、板垣退助らは政治結社である立志社を設立した。そして、1875年には立志社を中心に、全国の同志を集めて愛国社を結成した。
A.
政府はこれを時期尚早として却下した。
A.
政府はこれを拒否した。
A.
民衆が1881年の開拓使官有物払い下げ事件に対して強く批判したため、伊藤博文らは天皇に勧めて、国会開設の勅諭を出し、1890年に国会を開設することを約束した。(開拓使官有物払い下げ事件とは、北海道開拓使の黒田清隆が、関西貿易社に官有物を安く払い下げようとした事件。)
A.
自由党は、主権在民・一院制議会・普通選挙を掲げ、フランス流の急進的な自由主義を主張した。支持層は士族・豪農など。
A.
A.
立憲改進党は、君民同治・二院制議会・制限選挙を掲げ、イギリス流の穏健な立憲主義を主張した。支持層は都市の知識人や商業資本家(特に三菱)など。
A.
A.
A.
A.
薩長土肥の4つの藩は、それぞれ薩摩藩・長州藩・土佐藩・肥前藩。
A.
欽定憲法とは、君主の単独の意志によって制定される憲法のこと。大日本帝国憲法では、主権は天皇にあり、軍隊を指揮する統帥権や外国と条約を結ぶ権利なども天皇にあった。
A.
A.
A.
A.
投票率は約94%と高かったが、選挙権を持った人は、当時の日本の全人口に対して1.1%とわずかであった。
日清戦争・日露戦争
A.
東学とは民間宗教の1つ。朝鮮は清に救援を求め、清は軍を送った。一方で、日本も清と結んだ天津条約を口実に出兵した。その後、清軍と日本軍の対立が深まり、日清戦争へとつながる。
A.
A.
主な内容としては、①清国は朝鮮の独立を認める、②清国は遼東半島・台湾・澎湖諸島を日本へ割譲する、③清国は日本に賠償金2億両(約3億円)を支払う、などがある。
A.
下関条約で日本の遼東半島領有が規定されていた。
A.
A.
A.
植民地化を進め、北のカイロと南のケープタウンを結ぼうとした。
A.
植民地化を進め、西アフリカ・サハラ地域と東のジブチを結ぼうとした。
A.
清は「眠れる獅子」と恐れられていたが、日清戦争で日本に敗れると、列強は清に進出するようになった。こうして、列強の中国分割がなされた。
A.
義和団とは宗教結社の1つ。義和団は「扶清滅洋」(清を助け、西洋を滅ぼす)を掲げ、列強の中国進出に反発した。
A.
ロシアは満州を占領していたが、日本は韓国から満州に進出したいと考えており、問題となっていた。また、イギリスもロシアの南下政策により、中国やインドの利益をおびやかされていた。そこで日本とイギリスの利害が一致した。
A.
キリスト者(教徒)の内村鑑三や社会主義者の幸徳秋水・堺利彦らは、『万朝報』の記者として、非戦論を主張していた。
A.
1905年5月、日本海海戦で、東郷平八郎の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊(ロシア最大の艦隊)を破った。しかし、日本は戦争を続ける余力がなく、アメリカ第26代大統領のセオドア=ルーズベルトにロシアとの講和を依頼した。
A.
日本側の代表は小村寿太郎、ロシア側はウィッテ。条約の内容は、①ロシアは日本の韓国における指導権を承認、②旅順・大連の租借権と長春以南の鉄道とその付属の利権を日本に譲渡、③北緯50度以南の樺太を日本に割譲、④沿海州・カムチャツカ半島沿岸の漁業権を日本に承認、など。
A.
不満を持った国民が東京の日比谷公園に集まり、講和の反対を唱え、警察署・新聞社などを襲った。
欧米諸国との条約改正
A.
岩倉使節団(岩倉遣外使節団)という。
A.
日本は欧化政策を行うことで、欧米の理解を得ようとした。井上馨は東京の日比谷に、コンドルの設計による鹿鳴館を建て、舞踏会を催すなどした。
A.
ノルマントン号事件とは、和歌山県の沖合でイギリスの貨物船ノルマントン号が沈没し、イギリス人船員は皆ボートに乗り助かったが、日本人は全員溺死したという事件。
A.
A.
領事裁判権の撤廃・関税自主権の一部回復・相互的な最恵国待遇などが認められた。その後、他の欧米諸国とも同様の条約を結んだ。
A.
A.
その後、他の欧米諸国とも同様の条約を結んだ。
韓国併合と中華民国の成立
A.
統監府は日本政府の官庁。伊藤博文が初代統監となった。1897~1910年、朝鮮では高宗が国名を大韓帝国(韓国)に改称した。
A.
首都を漢城から京城と改め、そこに朝鮮総督府を設置した。
A.
略して満鉄ともいう。満州の植民地支配に大きな役割を果たした。
A.
孫文は中国同盟会を結成した。
A.
三民主義とは、民族主義・民権主義・民生主義のこと。
A.
辛亥革命がおこり、中国の多くの省は清からの独立を宣言した。
A.
その後、清の袁世凱は中華民国と取引をし、清の皇帝を退位させ、中華民国の臨時大総統となった。
日本の産業革命と社会問題
A.
A.
1882年、渋沢栄一らが大阪紡績会社を設立し、イギリス製の機械と蒸気力を利用した近代的紡績工場を建てた。その後大規模な紡績会社が次々と設立され、1897年には綿糸の輸出量が輸入量を上回った。
A.
日露戦争の前後に、機械・鉄鋼などの重工業で産業革命がおこった。
A.
A.
寄生地主は1880年代頃に急成長した。
A.
A.
このことを足尾鉱毒事件という。社会問題となった。
A.
A.
労働者は労働組合を結成したり、ストライキをおこしたりして、経営者と対立した。
A.
その後幸徳秋水らは平民社を設立し、『平民新聞』を発行した。
A.
A.
近代文化・教育・科学
A.
A.
学校令は小学校令・中学校令・師範学校令・帝国大学令からなる。尋常小学校の義務教育については、小学校令で規定された。なお、1872年の学制で義務教育の方針がとられ、次第に期間を延ばし、1907年には義務教育は6年となった。
A.
「教育ニ関スル勅語」が一般的に教育勅語といわれている。忠君愛国とは、主君(天皇)に忠義を尽くし、国を愛すること。
A.
A.
A.
A.
写実主義とは、現実をあるがままに再現しようとする芸術上の方針・考え。
A.
A.
A.
A.
A.
森鷗外は、晩年、歴史小説を多く書いた。ロマン主義の影響を受けた者には、島崎藤村や与謝野晶子などがいる。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
団・菊・左はそれぞれ、九代目市川団十郎・五代目尾上菊五郎・初代市川左団次を表す。
A.
新劇では、シェークスピアなどの翻訳劇などが演じられた。なお、新劇は新派劇とは異なる。新派劇とは、古い歌舞伎に対して、明治中期におこった新しい演劇のこと。
第一次世界大戦
A.
A.
A.
A.
A.
セルビアは1908年のオーストラリアによるボスニア・ヘルツェゴビナ併合に不満を持っていた。
A.
日本は第2次大隈内閣の時、日英同盟を根拠としてドイツに宣戦布告し、連合国側の一員として第一次世界大戦に参戦した。
A.
これまでの軽工業・重工業に加えて、化学工業が成長した。大戦景気で大きな利益を得た者を成金という。特に、造船・海運における成金を、船成金という。
A.
第2次大隈内閣は、第一次世界大戦によってヨーロッパ諸国が中国問題に介入する余裕はないと考えた。
A.
当時の中国は中華民国という。
A.
これを十一月革命という。
A.
A.
A.
A.
A.
第一次世界大戦は、1917年にアメリカの参戦により連合国側が有利となった。その後、1918年にロシアが連合国側を離脱したが、1918年11月にドイツで革命がおこり、第一次世界大戦は終結した。
A.
A.
ドイツは多額の賠償金を課せられ、ポーランドの独立も認められた。
A.
民族自決の原則はヨーロッパのみに適用され、アジア・アフリカには適用されなかった。
A.
ヴァイマル憲法ともいう。当時、世界で最も民主的な憲法とされた。
A.
当初、常任理事国はイギリス・フランス・イタリア・日本の4か国。アメリカは上院に否決され、加盟しなかった。
A.
太平洋諸国について4か国条約、中国について9か国条約が結ばれた。日本はアメリカによって、中国への進出を抑止された。
A.
A.
三・一事件ともいう。1919年3月1日におこった。
A.
1919年5月4日におこった。二十一か条の要求の解消を求めたが、それを拒否されたことから五・四運動がおこった。中国政府もこの運動に支えられ、ベルサイユ条約の調印を拒否した。
A.
大正デモクラシー
A.
尾崎行雄は「憲政の神様」とよばれた。
A.
陸軍・藩閥の第3次桂太郎内閣が成立したが、尾崎行雄らと民衆は陸軍・藩閥政治に反対し、「閥族打破・憲政擁護」を掲げて第一次護憲運動を展開した。その結果、第3次桂内閣はわずか53日で退陣に追い込まれた。(大正政変)
A.
米騒動は富山県から始まり、全国に広まった。
A.
吉野作造は民本主義を、美濃部達吉は天皇機関説を唱えた。
A.
A.
普通選挙と政党政治の実現を説いた。
A.
大正デモクラシーでは普通選挙が求められていたが、原敬は普通選挙には反対しており、納税資格を3円に引き下げるだけの制限選挙にとどまった。また、立憲政友会に有利な小選挙区制を採用した。しかし、原敬はこれらに不満を持つ者に東京駅で刺殺された。
A.
政党内閣とは、議会で多数を占める政党により組織された内閣のこと。
A.
護憲三派とは、憲政会・立憲政友会・革新倶楽部の3党のこと。
A.
護憲三派は1924年の選挙で圧勝し、衆議院第一党となった憲政会総裁加藤高明が首相となった。
A.
普通選挙法は衆議院議員選挙法を改正したものの通称。納税資格の制限が撤廃された。
A.
普通選挙法の実施やソ連との国交樹立によって、共産主義・社会主義・無政府主義運動の拡大を防止する目的があった。
A.
平塚雷鳥ともいう。1920年には、市川房枝らとともに新婦人協会を設立。
A.
A.
メーデーとは、毎年5月1日に行われる労働者の世界的な祭典のこと。1886年5月1日にアメリカのシカゴで、労働者が8時間労働制を要求してストライキしたことを記念している。
A.
コミンテルンとは、モスクワに創設された共産主義政党の国際組織のこと。
A.
A.
死者・行方不明者は10万人以上。経済的にも大きな被害を受け、不況が深刻化した。1927年には金融恐慌がおこり、銀行・会社の破綻・倒産が相次いだ。一方で、三井・三菱・住友・安田・第一の5大銀行に預金が集中し、財閥の基盤が強化された。
A.
A.
大衆雑誌には、『キング』や『講談倶楽部』などがある。映画は19世紀末に活動写真が輸入された。当初は無声映画だったが、1930年代に入り、画面と音声が一体のトーキーが現れた。
A.
和風の住宅に、洋風の応接間を持つ。サラリーマンを中心とする新中間層が住んだ。
世界恐慌と各国の動き
A.
A.
ソ連を除く各国で、銀行・会社の破綻・倒産が相次いだ。
A.
A.
ニューディールとは「新規まき直し」という意味。従来の自由放任主義的な政策から、政府による積極的な経済統制に転換した。テネシー川流域開発公社(TVA)による公共事業などがある。
A.
第三国に対し関税障壁をもうけた。
A.
A.
ファシズムとは、国内では極端な国粋主義で独裁政治を行い、対外的には侵略主義をとる政治運動・体制をいう。イタリアからヨーロッパ各国に広まった。
A.
A.
A.
1927年4月12日に上海クーデターをおこし、その6日後の4月18日、蔣介石は南京に南京国民政府を成立させた。そして、1928年には北伐(北部の軍閥との戦い)を完成させ、中国統一を果たす。
A.
第二次世界大戦後、1949年に中華人民共和国を樹立した。
A.
A.
労働争議や小作争議が相次いだ。
A.
軍部の台頭
A.
A.
A.
溥儀は1934年に皇帝となり、帝政をしいた。
A.
A.
これにより、1924年以来続いた政党政治が終わった。
A.
1932年、国際連盟はリットン調査団を満州事変の調査に派遣し、日本に対して満州国から軍を引き上げるよう勧告した。その後、国際連盟総会でもその勧告について採決し、42対1(反対1は日本)で可決した。そのため、全権を持つ松岡洋右ら日本代表団はすぐに退場した。
A.
軍部は反乱軍を鎮圧し、統制派が皇道派を一掃した。また、軍部が実力行使に出る可能性があるとの威圧効果もあり、軍部(特に陸軍)は発言権を増していった。
A.
1936年11月、コミンテルンによる共産主義拡大に対して、日本とドイツで日独防共協定を結んでいた。
A.
A.
日中戦争は第二次世界大戦で日本が降伏する1945年8月まで続いた。
A.
A.
A.
第二次世界大戦
A.
1935年、ドイツのヒトラー政権は、ヴェルサイユ条約の軍事制限条項を破棄し、ドイツの再軍備を宣言していた。1941年、ドイツは独ソ不可侵条約を破り、ソ連への侵攻を始めた。
A.
第二次世界大戦は、1943年9月にイタリア、1945年5月にドイツ、1945年8月に日本が降伏して終わる。
A.
A.
A.
大政翼賛会の下部組織として隣組がつくられ、住民はお互いに監視し合うようになった。
A.
A.
A.
A.
大東亜共栄圏とは、アジアを欧米の支配から解放し、日本を中心として共存共栄していこうとする構想をいう。
A.
A.
多くの男性が徴兵され労働力不足になったため、学生・女性らを軍需産業に動員した。これを勤労動員という。
A.
大都市の学童(小学生)を集団で疎開させることを学童疎開(集団疎開)という。
A.
ヤルタ会談では国際連合の設立などについても協議された。1945年8月8日、ソ連は日ソ中立条約を破棄し、日本に宣戦布告した。そして、9日には満州・朝鮮・千島列島に進攻した。
A.
A.
翌15日、天皇はラジオ放送で国民に終戦を知らせた。
現代
日本の戦後改革と主権回復
A.
A.
GHQの指示のもとに日本政府が統治をする間接統治の方式がとられた。こうして、GHQより五大改革指令などが出され、日本政府は戦後改革を行った。
A.
A級戦犯では、東条英機ら7人が死刑となった。また、天皇の責任は問われなかった。
A.
GHQは財閥と寄生地主制が日本の軍国主義の経済的基盤であると考えた。1947年には独占禁止法が制定された。
A.
小作地は、改革前に耕地全体の46%を占めていたが、改革後には10%に激減した。
A.
1946年の総選挙では、39人の女性議員が当選した。選挙権年齢は2015年に20歳から18歳に変更され、2016年から実施された。
A.
A.
A.
A.
A.
軍国主義の教育が禁止された。教育基本法には、教育の機会均等・9年間の義務教育・男女共学などが規定されている。
A.
単に特需、または朝鮮特需ともいう。
A.
朝鮮戦争でアメリカ軍のほとんどが朝鮮に渡ったため、日本国内には防衛・治安維持の兵力が残っていなかった。
A.
1952年に警察予備隊が保安隊に改組され、保安隊は海上の治安維持を担う警備隊とともに、保安庁の組織下に入った。
A.
内容は、戦争の終了と日本の主権回復、日本は朝鮮の独立を承認、朝鮮・台湾・澎湖諸島・千島列島・南樺太などの放棄など。
A.
中華人民共和国・中華民国は講和会議に招かれず、インド・ビルマ・ユーゴスラビアは招かれたが不参加、ソ連・ポーランド・チェコスロバキアは出席したが調印を拒否した。
A.
米軍の駐留や侵略・内乱に対する出動などが内容。1952年には日米行政協定を結び、米軍基地の無償提供や分担金の負担など、日本に不利な内容が定められた。
A.
日ソ共同宣言は鳩山一郎内閣のときに実現した。
A.
1958年には、日本は安全保障理事会の非常任理事国に選ばれた。
A.
岸内閣は対等な日米関係を求めた。新安保条約の内容は、アメリカの日本防衛義務、米軍の軍事行動の事前協議制、期限10年(自動延長)など。1959~60年には安保条約の改定に対して反対運動(安保闘争)がおこった。岸内閣は新安保条約に調印した後、1960年7月に総辞職した。
冷戦と各国の動き
A.
日本は1956年に加盟した。
A.
常任理事国であるアメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中国の5大国は拒否権を持つ。大国一致の原則により、安全保障理事会の決議には、5大国全ての賛成が必要。つまり、5大国のうち1か国でも拒否すれば決議は否決される。
A.
ドイツは西ドイツと東ドイツに分断された。イギリスのチャーチル元首相は、東西両陣営の境界を「鉄のカーテン」と表現した。
A.
A.
A.
A.
日本が敗戦し中国から撤兵した後、毛沢東の率いる中国共産党と蔣介石の率いる中国国民党は内戦を始めた。共産党が勝利し、国民党による国民政府は台湾に逃れた。
A.
1948年、朝鮮南部に大韓民国が成立した。それに対抗し、同年、朝鮮北部に朝鮮民主主義人民共和国が成立した。
A.
1953年7月に朝鮮休戦協定が調印された。
A.
アジア・アフリカ会議にはアジア・アフリカの29か国が参加した。平和十原則の内容は、主権・領土の尊重や平和共存など。
A.
1954年にアメリカが行ったビキニ水爆実験により、日本の漁船が放射能汚染を受けた(第五福竜丸事件)。その後、東京の主婦によって原水爆禁止運動が行われた。
A.
地下を除く、大気圏内・宇宙空間・水中での核爆発を伴う実験を禁止した。
A.
NPTは核兵器不拡散条約とも訳される。すでに核を持つ5か国は、アメリカ・ソ連・イギリス・フランス・中国。北朝鮮は1993年に脱退。インド・パキスタン・イスラエル・南スーダンは未加盟。(2016年6月2日現在)
A.
戦争の開始時期には諸説ある。1965年にアメリカが北ベトナムを爆撃し本格的に介入してから、ベトナム戦争は泥沼化していった。1973年にアメリカ軍が軍を撤退して、戦争は終結に向かった。1975年、南ベトナム政府が崩壊し、1976年に南北が統一された。
A.
原加盟国はタイ・インドネシア・シンガポール・フィリピン・マレーシアの5か国。
A.
A.
日本は韓国を朝鮮半島における唯一の政府と認め、国交を回復した。そして、日本は韓国へ無償の経済援助を決定した。
A.
日本は中華人民共和国を唯一の合法な政府であると認めた。これにより日中国交正常化が実現したが、台湾の国民政府との国交は断絶した。
A.
A.
A.
A.
ペレストロイカはロシア語で「建て直し」を意味する。影響は東ヨーロッパにも波及し、東ドイツが西ベルリンを囲むように建設したベルリンの壁も、1989年に開放された。1990年には西ドイツが東ドイツを吸収し、ドイツは統一された。
A.
1991年にソ連が解体し、ロシア共和国はロシア連邦となった。ロシア連邦が国連の代表権などの権利をソ連から継承した。そして、ソ連を構成していた国々はロシア連邦を中心として独立国家共同体(CIS)というゆるやかな共同体を形成した。
A.
EUの単一通貨にはユーロが使われている。
A.
A.
先進国は北半球に多く、発展途上国は南半球に多いことから、南北問題という。
A.
日本の高度経済成長
A.
A.
1956年、経済白書(年次経済報告書)で「もはや戦後ではない」と記され、日本経済が戦後の混乱期を抜けたことを象徴した。そして1968年には、日本は国民総生産(GNP)がアメリカに次ぐ世界第2位となった。
A.
A.
3Cはカラーテレビ(Color television)・クーラー(Cooler)・自動車(Car)の頭文字をとったもの。
A.
A.
A.
A.
A.
1967年に公害対策基本法が制定され、1993年より環境基本法に引き継がれた。また、1971年に環境庁(2001年から環境省)が設置された。
A.
A.
A.
A.
A.
石油危機はオイルショックともいう。激しい物価上昇(狂乱物価)がおこった。そのため、戦後初めて経済がマイナス成長となり、高度経済成長は終わりを迎えた。また、1979年には、イラン革命をきっかけに原油価格が上昇し、第二次石油危機がおこった。
A.
当時アメリカは「双子の赤字」という、財政赤字と貿易赤字に苦しんでいた。