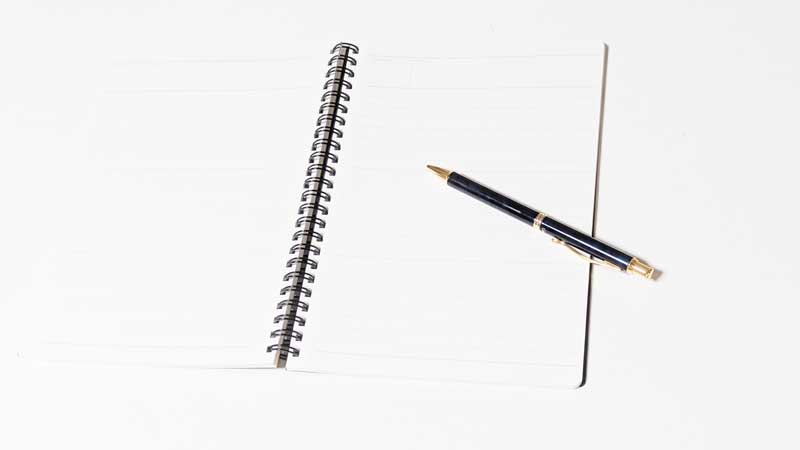身のまわりの物質
身のまわりの物質とその性質
A.
例えば、窓を構成する物質はガラスである。
A.
例えば、ガラスが集まって窓がつくられる。
A.
金属の特徴: ①熱・電気をよく通す、②金属光沢がある、③展性(圧力・打撃などでうすく広がる性質)・延性(引っ張ると伸びる性質)をもつ、④密度が大きい、⑤融点・沸点が高い
A.
A.
A.
有機物は、例えば砂糖・アルコール・紙などがある。
A.
二酸化炭素や石灰岩など、炭素を含んでいても無機物に分類されるものもある。これは、もともとの分類が動物・植物から得られるものを有機物、鉱物から得られるものを無機物と定義していたためである。(現在は炭素による分類となっている。)
A.
プラスチックの中で、ポリ塩化ビニル(PVC)は消しゴムなど、ポリエチレンテレフタラート(PET)はペットボトルなどに使われる。
A.
A.
A.
A.
目盛りは液面の最も低い位置を読み取る。1目盛りの1/10までを目分量で読み取る。
A.
密度の単位には、g/cm3がよく使われる。
A.
火のつけ方: ①ガス調節ねじと空気調節ねじが閉まっていることを確認する、②元栓(とコック)を開ける、③マッチなどに火をつける、④ガス調節ねじを少しずつ開き点火する(ほのおの大きさを調整)、⑤ガス調節ねじをおさえながら、空気調節ねじを開き、青色のほのおにする
火の消し方: ①空気調節ねじを閉じる、②ガス調節ねじを閉じる、③(コックを先に閉じてから、)元栓を閉じる
気体の発生と性質
A.
アンモニアなど。
A.
二酸化炭素・塩素など。
A.
酸素・水素など。二酸化炭素も水に少しとけるが可能。
A.
その他の成分はアルゴン・二酸化炭素・ネオン・ヘリウムなど。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
lはLの小文字。
A.
A.
lはLの小文字。
A.
A.
A.
物質の溶解
A.
物質が水に溶けたものを特に水溶液という。
A.
A.
A.
A.
ろ過を行うときに使う紙をろ紙という。ろ紙は4つに折り、円すい形にしてろうとにつける。ろ過は液体をガラス棒に伝わらせながら少しずつろ紙に注ぐ。ろ紙を通過した液体をろ液という。
A.
質量パーセント濃度(%) = 溶質の質量(g) ÷ 溶液の質量(g) × 100
溶液の質量(g) = 溶質の質量(g) + 溶媒の質量(g)
溶解度と再結晶
A.
溶媒は指定されない場合はふつう水をさす。
A.
A.
A.
塩化ナトリウムは食塩ともいい、水溶液は中性を示す。中和反応によって生じるものを塩という。lはLの小文字。
A.
A.
A.
不純物が除かれ、純度の高い結晶が得られる。
状態変化と熱
A.
A.
固体から直接気体に変化することを昇華という。
A.
液体の内部からも気体に変化することを沸騰という。また、液体から気体に変化することを気化ともいう。
A.
液化・凝結ともいう。気体から直接固体に変化することを凝華という。
A.
A.
A.
A.
物質それぞれの融点・沸点がある。
A.
一定の融点・沸点がない。
A.
A.
A.
化学変化と原子・分子
物質の分解
A.
化学変化とは別に、物質そのものは変化せず、その状態が変化することを物理変化という。例えば、固体・液体・気体の状態変化や溶質・溶媒が混ざり合う溶解などは物理変化である。
A.
熱分解・電気分解などがある。
A.
A.
A.
酸化銀の化学式はAg2O
A.
A.
水を電気分解すると、陰極では水素が発生し、陽極では酸素が発生する。
原子・分子
A.
原子の構造は、中心に中性子と陽子で構成された原子核があり、その周りに電子が分布している。
A.
同じ元素でも中性子の数が異なる原子を同位体という。
A.
原子記号ともいう。
A.
周期律とは、元素を原子番号順に並べると、一定の周期で性質の似たものがあらわれるという法則である。
A.
原子が結合したもの。
結びつき
A.
元素記号・分子式・組成式は化学式である。
A.
A.
A.
A.
A.
酸化と還元
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
化学変化と熱
A.
発熱反応では温度は上がる。鉄粉と活性炭を混ぜたものに食塩水を加えると、鉄が酸化し、熱が発生する。活性炭は空気中の酸素を吸着し、鉄粉の酸化をはやめる。
A.
吸熱反応では温度は下がる。
化学変化と物質の質量
A.
化学変化とイオン
水溶液の電気伝導性
A.
電解質は水に溶けると電離する。電離とは、陽イオンと陰イオンに分離すること。
A.
A.
原子の構造は、中心に中性子と陽子で構成された原子核があり、その周りに電子が分布している。
A.
原子が電子を過剰に受け取った場合は陰イオンとなり、原子が電子を失い不足した場合は陽イオンとなる。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
化学変化と電池
A.
A.
化学電池の電流が流れたことを確認することなどに使われる。
A.
酸・アルカリ
A.
酸の性質が強いものを強酸という。逆に酸の性質が弱いものを弱酸という。
A.
A.
濃硫酸には脱水性・吸湿性がある。
A.
A.
A.
A.
アルカリの性質が強いものを強アルカリという。逆にアルカリの性質が弱いものを弱アルカリという。
A.
水酸化ナトリウムは苛性ソーダともいう。
A.
A.
A.
青色リトマス紙は酸性で赤色になる。赤色リトマス紙はアルカリ性で青色になる。
A.
A.
中和と塩
A.
中和反応ともいう。
A.
A.
A.
A.
この場合の炭酸カルシウムは中和により生じた塩である。
元素記号・化学式
物質名
A.
A.
A.
A.
A.
lはLの小文字。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
lはLの小文字。
A.
A.
lはLの小文字。
A.
A.
A.
元素記号・化学式
A.
A.
A.
A.
A.
lはLの小文字。
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
lはLの小文字。
A.
A.
A.